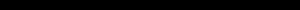mintdesignsは2003年の東京コレクション初参加以降、毎シーズンランウェイショーを披露。東京を代表するブランドとして様々な賞を受賞し2010年には第28回毎日ファッション大賞を受賞している。
2011 – 2012 A/W Collectionは2011年4月9日TABLOIDにてランウェイショーを開催。”Fashion Surgery”をテーマに一つ一つに対してはシンプルで無機質な記号的な柄をモチーフにしたり、テキスタイルも格子柄等を組み合わせてカッティングやつぎはぐ位置を変えることで意味を持たせ、集合体になることで強さを生み出している。今コレクションは震災後に新たに掲げた”A New Hope”のイメージに合わせスタイリングや構成など新たに組み直されている。
彼らの提案した最新コレクションにファッション編集者たちはどんな評価をしたのだろうか。今回はmintdesignsのコレクションを過去幾シーズンにも渡り見続けてきた、雑誌ハイファッションの編集長を務めた田口氏、high fashion ONLINEの西谷氏、繊維ニュースの増田氏の3名にショーのコメントをお願いした。
→mintdesigns 2011-2012 A/W Collection
———————————————————————————————————————————–
「ミントデザインズ」の印象を一言で言うと「不変」です。反抗期でもデニムのみに絞っても、印象がいつも変わらない。半年ごとに変化を求められがちなランウェイショーという舞台に立ち続けながら、軸がぶれないんですね。一方で、不変のスタイルの中に時事や気分を上手く落とし込んでくるから、何となく新しいものを見たような気にもさせてくれる。11AWも色使いやジャケットのパターンに新しさを感じましたが、全体を支配する「雲の上を歩いているような浮遊感と体温の低いドール的な女性像」は不変だった。また、お二人とも弁が立つので、社会の変化を洋服に投影したような評価を受けがちですが、個人的には服からのメッセージ性を強く感じたことはありません。
コレクションブランドにとって「変わらない」ということはネガティブにもとれますが、僕はそれが悪いことだとは思わない。展示会ベースで不変の世界観をコツコツと進化させるブランドは東京にたくさんありますが、ミントはそういうスタンスを東コレという舞台で貫いている気がする。ビジネスという観点で見ても、今はその手法が正解で、東コレ組では珍しくビジネスを軌道に乗せているという点でも評価できると思います。決して一般的な服ではなくいわゆるモテ服でもないので、店頭でも街でも見かける機会は決して多くありませんが、渋谷パルコの直営店を中心にコアな顧客をつかんでいる印象を受けます。
彼らの武器は軽やかな雰囲気とテキスタイルデザインにあると思います。とくにテキスタイルは「マリメッコ」みたいにそれ単独で商品になる可能性を秘めている。プロダクト的なアプローチに秀でていると思うので、今後は洋服だけではなく様々なプロダクトデザインにも挑戦してほしいですね。ミントデザインズなクルマなんて、想像するだけで楽しくなってしまいます。
増田海治郎 / 繊維ニュース 記者
———————————————————————————————————————————
ミントデザインズの「Cold Feaver」
10年を迎えたミントデザインズ。初期のミントデザインズが、東京コレクションの常識に屈することなく、発表場所も方法もその都度変えて、実験的なプレゼンテーションを行ったことを知る人も今や少ないのかもしれない。ファッションジャーナリズムからは、よくぞこういう方法で見せてくれたという好意的な驚きの声が上がることもあれば、黙殺、あるいは、「これってファッション?」というおキマリの反発が来ることも。ともかく、彼らは、既成のファッション言語の中に自分たちを当てはめることを潔しとせず、戦い、傷つき、しかしひるまず、自らのスタイルを確立してきたのだ。
昨年毎日ファッション大賞を受賞した時のインタビュー(http://fashionjp.net/highfashiononline/feature/collection/mintdesigns_11ss.html)でも「デビューしてから7年間くらい、自分たちはモードにおける本流ではないと思っていましたので、まず意外な気持ちがありました」と語っている。
「モード」(それにしても、なんという曖昧な言葉)の「傍流」として、ミントが一貫して追求してきたのは、プロダクトデザインとしての強度を持った服であり、そのためのファッション的な環境整備、とでもいえるものだ。ショーとしての水準を保つために、演出の金子繁孝、ヘアメークの加茂克也という最強のキャスティングを組み、毎回会場を変え、独自のショーを展開してきた。その積み重なりが、「本流」が存在を薄めて行く中、際立ってきたのが「10年」の意味だ。
震災後、多くのブランドがショーを自粛した中で、アンリアレイジと共同声明を出し、ミントデザインズがランウェイショーを決然と行ったのも、おそらく、この独自性の蓄積が公認のステータスを得始めていて、この流れを消すわけにはいかないという自覚であり、責任感からでもあると思う。
今回のテーマは“Fashion surgery”(ファッションの手術室)。Tabloidの天井と床に取り付けた蛍光灯が青白く強い光を放つ中、無機質なモチーフを使ったプリントや直線的なシルエットの服が病院の廊下のようなランウェイを歩いた。
いつもながら完成度の高いプレゼンテーションと、東京のブランドの中でも群を抜いた色彩感覚。
ミントの服は,形も色も北方系だ。とりわけ今回はその色が濃い。フィンランド、デンマーク、オランダなどのすぐれたデザイン感覚を持つ「北」の国と親和性を持つ、リアルでユーモラスな服。めまいがするようなハイヒールとボディコンシャスとフルメークのパリ、ミラノのラテン系商業主義とは決して相容れないクリエーションだ。
そこに私はとても好感を感じて、これまでミントの活動を見てきた気がする。“デザイン”に向き合うプロフェッショナルで安定した姿勢も好ましい。
しかし同時に、ミントは日本のファッション界の中では、きっとある種の生きにくさを感じているだろうと推察する。なぜなら、日本の業界は、なんといってもラグジュアリー信仰が根強いし、ファッションとは欲望渦巻くきらびやかなお祭りであって、その狂躁の中で、ものが売られ、買われていくことに意味を見つける人が主流派のようだから。多くの高級ブランドのレセプションが、シャンパンと芸能人とお愛想を3点セットにしているのを見るたびに悲しくなるのは、私だけではないと思うが。これって、決して日本から生まれた文化ではないでしょう。
これからのミントに期待したいのは、この10年の継続という成果を、新しいファッションのポジショニングに生かしてほしいということだ。そろそろパリコレ、というお誘いもあることと思う。でも、パリに行くなら、いくつかの価値観を一にするブランドを引き連れて、アントワープ勢がパリに乗り込んだときのように、堂々デビューしてほしい。そして、パリにない、日本のインディペンデントの価値観をアピールしてほしい。JFWは、そういうことをこそ支援すべきだと思うが、いかがだろう。
西谷真理子 / ハイファッション・オンライン チーフエディター
———————————————————————————————————————————–
雑誌編集長の頃は、優先せざるを得ない急な招集の会議などが多く、東京コレクションの取材は、一日に一つか二つが限界だったが、ミントデザインズは高い頻度で見てきた。おそらく自分の中に、ここのショーを見たいという欲求があり、 “必見ブランド”と位置づけていたからだと思う。
ミントデザインズのデビュー当時、東コレは「東京カワイイ」が主流。さらに、毎回スタイルの違うトレンド発信型。コンサバティブ。前衛的。演劇的な演出のショーなど、多種多様なコレクションの中で、ミントデザインズは、容易にカテゴライズのできない、柔らかな表現方法と透明感が逆に異色だった。これまでにない新しい価値観とリアリティを持つ世代のデザイナーの出現を感じたのである。
服の色彩やプリントのオリジナリティはもとより、ヘアメイク、音楽、照明、起用するモデルのタイプなど、あらゆる要素が分離することなくミントデザインズの全体像を形成し、ショー空間から提案される。彼らにとって欠くことのできないと推測される、アート的な要素の配分バランスも抑制されている。そこに勝井北斗と八木奈央、2人のデザイナーの、自分たちが作るものに対する客観性が感じられるのだ。
ミントデザインズは、03年春夏から東コレに参加し、ほぼ10年になる。シーズンごとの劇的な変化や沈滞といった乱高下のない、同じ立ち位置での10年という「継続」は、時代ごと転変を繰り返して来た東京コレクションの推移の中では異例ともいえる長さだ。プロダクトデザインを目指すという、ミントデザインズのブランドコンセプトが、揺るぎない「継続」に現れているのだと思う。それは、「東京コレクション」全体への信頼感や、一定のイメージのインプットにも繋がっていく貴重なことだと思っている。
田口 淑子