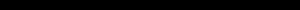2012 S/S collectionでは初のランウェイショー形式の発表を行なったNocturne #22 In C Sharp Minor, op. Posth.。 “detachable femininity(=取り外し可能の女らしさ)”というテーマのもと、ファッションの必要性、不必要性と相反する2つの価値観を内包しながら、それでも服を脱げば皆同じというスタンスでの服作りを提案し注目を集めている。
デザイナー鈴木道子氏は文化服装学院を卒業後、Yohji Yamamoto、Y’sのパタンナーを経験。その後Y’s Red Labelのデザイナーとしてキャリアを積む。そして2010年に自身のブランドNocturne #22、2011年にはヴィンテージラインであるNocturne #23をスタート。鈴木道子氏のクリエーションの源泉に迫るべく、話を聞いた。
―鈴木さんの名刺にはNocturneの他に「テイラー門脇」という会社名が書かれていますがテイラードの会社もやられているのですか?
祖父がテーラードを仕立てていました。それを引き継いだという格好になります。山形で代々受け継がれていて私で4代目になります。
オーダーでの取り扱いも行なっているので、デザインと言えるのかどうかわかりませんがお年寄りにオーダーメイドの服と、それとは別に仕入れた既製品を販売しています。昔はオーダーのほうが多かったみたいですが私が高校生の頃、祖父が「オーダーの時代は終わった」と呟いていました(笑)。
当時は市議会議員の方や校長先生とか立派な仕事をされている方が買ってくれていたようです。
―鈴木さんにとって幼少期から服は身近な存在だったんですね。
針に糸を通すことが子供の頃の仕事でした。英才教育ですね(笑)。
そこが作る場所でもあり、売る場所でもあるのでお客さんのおばあちゃんと話したりしていました。接客しているところをずっと見ていたので商売というものを肌で感じることができたと思います。今やっていることと変わらないですし、それが原点だと思っています。
―小さい頃からデザイナーを目指していたのでしょうか?
何か作る仕事をしたいという思いがありました。私の場合近くにあったものが洋服だったのでその流れでという感覚です。洋服はパターンを引けないと作れないので、学校で学ぼうと思い文化服装学院に進学することにしました。文化は母親が行きたかった学校だったようで母親に薦められたんです。
―実家ではパターンは教えてもらえなかったのですか?
実家のテイラーではパターンは引かないんです。生地に直接線を描いて大体で切ってしまう。それは経験がものをいう仕事ですから当時の私には分からなくて。
―文化生としての生活はどうでしたか?
まじめな学生だったと思います。縫ったりということは入る前からできていたので、パターンを学びたいという意識が強くありました。でも学校で学んだことが今の仕事に役立っているかといえばほとんど役立っていないかもしれません(笑)。
―どうしてYohji Yamamotoへ行こうと思ったのですか?
ブランドで経験を積みたかったので、ISSEY MIYAKE、Comme des Garçons、Yohji Yamamotoの3社だけを受けたんです。Yohji Yamamotoの募集時期が一番最後だったのですが、ISSEY MIYAKE、Comme des Garçonsは落ちてYohji Yamamotoだけ受かったんです。
―Yohji Yamamotoでは何をされていたんですか?
Y’s Red Labelでデザイナー、Y’sのパタンナーをしていましたがそれ以前にはYohji Yamamoto+Noirでも約2年間仕事をしました。Yohji Yamamotoにはトータルで9年いました。
今の自分はYohji Yamamotoで全てを学んだといっても過言ではありません。できることなら高卒で入りたかったなって思います。会社にいるときはYohji Yamamotoの看板を継ぐつもりでやっていましたし、今も意思は継いでいると思っています。
―Yohji Yamamotoを辞めてからNocturneを始めるまでの期間に、アーティストとパフォーマンスのようなことをしていたこともあったと思いますがそのことに関して教えてください。
アーティスト達をフランス大使館に集めて様々なイベントを数ヶ月に渡り行っていたのですがその一環として音楽家Benjamin Skepperとのコラボレーションで洋服製作と音楽の即興パフォーマンスをやりました。その時はファッションではなくアートの方面に進もうと思っていたのですが、海外のアーティストと話をしていると「ご飯もろくに食べられないんだろうな」という率直な感想を持ったんです。
アートって楽しそうにやっているという側面だけが見えがちですが内情はとても暗いんです。出てくる話が暗い話ばかりで、その傷を舐めあう感じがすごく嫌になってしまったんですよね。「もう無理」と思ってしまって。
そのときフランス人の友人に「洋服やかばんだったら売れるでしょう?絵売るより簡単でしょう?」と言われて、確かにそうだなって。
Yohji Yamamotoを辞めてから、正直「洋服とかもう作りたくない」という思いもありました。服を作りつづけることが辛いことも分かっているので生まれ変わったら絶対やらないだろうと思いますし。
でもそれでも今こうして続けているということは、まだ服を作っていたかったということなんだと思います。
―服作りのどこが嫌だったのですか?
今でも嫌ですよ。
半分はすごく嫌で半分は楽しいという気持ちです。
―それはYohji Yamamotoではコレクションを製作するだけでなく半年に1度ランウェイショーをやらなければいけなかったからですか?
それは違います。映像や写真等の見せ方もファッションにはありますよね。そういうことも考えていたし、他の表現方法も模索しましたけど、でも結局ランウェイに辿り着いてしまうんです。ミュージシャンが小さくてもライブハウスでやりたいと思うように、ランウェイには“生もの”そういう感覚があると思うんです。半年かけて作ったものが10分、15分で終わる。でもそこに全てがあると思いますし、モデルの気分など些細なことで内容が変わってくる。見ている人もそうだと思いますし、私自身もそういった生でしかできないことを試したいという思いもあります。デザイナーはフィナーレにランウェイを歩かなければいけない。それに乗り気ではなかったのですがY’s Red Labelの時に出て行くことになって、でもそこで見に来てくださった方々の反応や雰囲気を体感するという経験に味を占めてしまったんですよね。その時、光の輪のようなものが見えたんです。その後ランウェイからバックステージに戻ると倒れてしまって。それは多分暑かったからだと思うんですけど(笑)。
―Y’s Red Labelでのランウェイはご自身がやりたくてやったことだったのですか?
元々デザイナーになるつもりは無かったのですが、ランウェイは自分からやりたいと言ってやったことだったと思います。見てくれた人の心を掴むことに関して言えば、ショー形式での発表は適していると思います。